帯状疱疹予防接種について
更新日:2026年2月13日
令和7年度の対象者の方へ
令和7年度の対象者の方(下記参照)は令和8年3月31日まで助成を受けることができます。
対象の方には4月中旬に案内通知を郵送しています。事前に医療機関に予約のうえ、接種してください。
組換えワクチンを選択した場合、2回接種する必要があり、完了するまでに約2か月かかります。接種を希望する方は令和8年1月末までに接種を開始することをご検討ください。令和8年4月1日以降は全額自己負担となります。
例1)組換えワクチンを選択し、令和8年1月に1回目接種、令和8年3月に2回目接種
⇒1回目、2回目ともに助成対象
例2)組み換えワクチンを選択し、令和8年2月又は3月に1回目接種、令和8年4月以降に2回目接種
⇒1回目のみ助成対象、2回目は全額自己負担
※4月以降に転入された方で接種を希望する場合は担当課へお問い合わせください。
帯状疱疹予防接種の費用を一部助成します
令和7年4月から予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、「定期接種」として実施します。
「B類疾病」とは・・・個人の発病または重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合に実施されるもので、努力義務は課せられていません。
帯状疱疹とは
帯状疱疹とは、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏したウイルスが、加齢や疲労による免疫力の低下により、ウイルスが再活性化することで発症し、水ぶくれを伴う発疹が皮膚に分布している神経に沿って帯状に出現する疾患です。合併症の一つに皮膚症状が治った後も痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。また、帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹の予防と治療
予防について
帯状疱疹は、免疫力の低下によって発症するため、帯状疱疹の予防には、日頃の体調管理が重要です。食事や睡眠をしっかりととり、適度な運動や、リラックスした時間をもつことでストレスを減らし、免疫力を低下させないように心がけましょう。
治療について
治療の中心は、ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬です。より早期の投与が効果的といわれていますので、痒みや痛みのあとに水疱が出現したりしたときは、できるだけ早く受診しましょう。
定期接種対象者
| 制度内容 | |
| 接種対象者 |
|
| 経過措置対象者 |
|
※既に生ワクチン1回または組換えワクチン2回を接種済みの方は、医師が必要と認める場合を除き、原則接種対象外です。詳しくはかかりつけ医に相談してください。
※5年間の経過措置対象者(令和7年4月~令和12年3月末まで)は、年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる方等)が対象となります。
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
| 70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
| 75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
| 80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
| 85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
| 90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
| 95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |
| 100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 |
| 100歳以上 | 大正14年4月1日以前に生まれた方 |
帯状疱疹ワクチンとは
帯状疱疹ワクチンには
- 生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)
- 組換えワクチン(GSK社:シングリックス)
の2種類があり、どちらかを選択して接種します。接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。個別案内通知に同封の説明書をよくお読みください。
| 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
|---|---|---|
接種回数 | 1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) |
| 接種スケジュール | ー | 2か月以上の間隔をおいて2回接種 ※医師が必要と判断した場合は接種間隔を 1か月まで短縮可 |
| 接種できない方 |
| ー |
| ※接種前に発熱(37.5度以上)している方、重篤な急性疾患に罹っている方、それぞれの予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな方等はいずれのワクチンも接種できません | ||
接種に注意が |
|
|
| ※心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方、免疫不全と診断されている方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、帯状疱疹ワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方等はいずれのワクチンの接種についても注意が必要です。 | ||
| 効果 |
(帯状疱疹後神経痛に対する予防効果:接種後3年時点で6割程度) |
(帯状疱疹後神経痛に対する予防効果:接種後3年時点で9割以上) |
主な副反応の |
|
|
| 他のワクチンとの接種間隔 | 他の生ワクチンと27日以上の間隔が必要 | ー |
接種回数、助成金額
| ワクチンの種類 | 接種回数 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 生ワクチン(阪大微研) | 1回 | 4,000円 |
| 組換えワクチン(GSK社) | 2回 | 11,000円/回 |
接種費用(医療機関によって異なります。)から上記の助成金額を引いた額が自己負担額となります。
対象の方のうち、生活保護世帯の方は事前に減免申請を行うことで自己負担額なく接種することができます。
生活保護世帯の方は接種する前に保健福祉課(A棟1階10番窓口)で申請してください。
実施場所
●![]() 協力医療機関(PDF:166KB)
協力医療機関(PDF:166KB)
掲載の医療機関以外にも、県内の協力医療機関で接種できます。
庄内地域以外の医療機関で接種を希望する場合は直接医療機関へ問い合わせてください。
持ち物
- マイナンバーカード・資格確認書等
- 自己負担金
※必要書類は医療機関に設置しています
予防接種救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こる場合があります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
詳細はこちらをご覧ください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
保健福祉課 健康推進係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0147

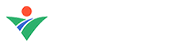
 くらしの情報
くらしの情報 行政情報
行政情報 産業・ビジネス
産業・ビジネス 観光・イベント
観光・イベント