子どもの定期予防接種
更新日:2025年12月1日
予防接種を受けて病気を予防しましょう
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした免疫は、生後数か月を過ぎると自然に失われていきます。
赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防するために、予防接種はとても重要です。
予防接種には、その病気にかかりやすい時期を考慮した“標準的な接種期間”が定められているので、できるだけこの期間内の早い時期に接種するように、スケジュールを立てましょう。
予防接種法で定められている以下の定期予防接種は、予防接種協力医療機関で無料で受けられます。(ただし、接種対象年齢を過ぎると任意接種となり、全額自己負担になりますのでご注意ください。)
※対象年齢に関する用語について…“〇歳に至るまで”や“〇歳未満”は〇歳の誕生日の前日までのことです。
例:「3歳に至るまで」…令和5年7月24日生まれであれば、令和8年7月23日まで接種できます。
麻しん風しんの定期予防接種の特例措置について
麻しん風しん混合ワクチンについては、一部のメーカーで出荷停止があったことから、令和6年度においてワクチンの供給不足が続いていました。このため、令和6年度の麻しん風しんの定期予防接種の対象者で、ワクチンの供給不足により対象年齢で予防接種を受けられなかった場合は、公費負担で接種できる期間を2年間延長する特例措置が設けられます。特例措置による予防接種を希望する場合は、医療機関にご相談ください。
予防接種の対象者
| 対象年齢 | ■ロタリックス(1価)生後24週未満 ■ロタテック (5価)生後32週未満 |
|---|---|
| 回数 | ■ロタリックス 2回 ■ロタテック 3回 ※2回目以降は前回の接種から27日以上あける。 |
| 標準的接種期間 | 1回目:生後2月から14週6日(約3月半)までに開始 ※14週6日を過ぎると接種できない場合があります。 |
| 対象年齢 | 生後2か月以上5歳未満 | |
|---|---|---|
| 標準的接種期間 | 初回接種開始:2か月以上7か月未満 追加接種:初回終了後60日以上あけて、1歳以上1歳3か月未満に1回 |
|
| 接種開始時期 と回数 |
初回の接種開始が 2か月以上 7か月未満 |
初回:3回…それぞれ27日以上あけて受ける ※3回目および3回目は2歳未満までに終了させる。2歳を超えた場合は行わない。 ※また、2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない。 追加:1回…初回3回目から60日以上あけて1歳以降に受ける |
| 初回の接種開始が 7か月以上 12か月未満 |
初回:2回…それぞれ27日以上あけて受ける ※2回目は2歳未満までに終了させる。2歳を超えた場合は行わない。 追加:1回…初回終了後60日以上あけて1歳以降に受ける |
|
| 初回の接種開始が 1歳以上 2歳未満 |
2回:60日以上あけて受ける | |
| 初回の接種開始が 2歳以上 5歳未満 |
1回 | |
令和6年4月から15価ワクチンが、10月からは20価ワクチンが定期接種となりました。接種スケジュールの変更はありません。
| 対象年齢 | 1歳未満 |
|---|---|
| 回数 | 3回 ※2回目は1回目の接種から27日以上あける ※3回目は1回目の接種から139日以上あける |
| 標準的接種期間 | 1回目:生後2月 2回目:生後3月 3回目:生後7月から8月 |
| 備考 | 母子感染予防のために、抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受ける場合は健康保険が適用されるため、定期接種の対象外となります。 |
| 対象年齢 | 1歳未満 |
|---|---|
| 回数 | 1回 |
| 標準的接種期間 | 生後5か月以上8か月未満 |
| 対象年齢 | 生後2か月以上7歳6か月未満 |
|---|---|
| 標準的接種期間 | 初回接種開始:生後2か月以上7か月未満 |
| 回数 | 1期初回:3回…それぞれ20日以上あけて受ける |
| 対象年齢 | 生後1歳以上3歳未満 |
|---|---|
| 回数 | 2回 ※3月以上あける |
| 標準的接種期間 | 1回目:1歳以上1歳3か月未満 2回目:1回目の接種後6か月以上12か月未満あけて1回 |
| 備考 | 水痘にかかったことがある場合は、対象外となります。 |
| 対象年齢 | 11歳以上13歳未満 |
|---|---|
| 標準的接種期間 | 11歳 |
| 回数 | 1回 |
| 備考 | 小学6年生に案内文書を送付します。 |
| 対象年齢 | 1期:1歳以上2歳未満 2期:5歳以上7歳未満で小学校入学の年の前年度中 ※幼稚園の年長クラス等の1年間(4月~翌年3月末)のみが対象となります。 ※5歳であっても幼稚園の年中クラスのお子さんは対象ではなく、また、6歳であっても小学1年生は対象ではありません。 |
|---|---|
| 回数 | 1期:1回 2期:1回 |
| 備考 | 麻しんと風しん両方にかかったことがある場合は、対象外となります。 |
※令和6年度に接種の対象となっていた方のうち、ワクチンの偏在等で期間中に接種を受けられなかった方は、経過措置が設けられています。接種については医療機関にご相談ください。
経過措置(接種)期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
| 対象年齢 | 1期初回:生後6か月以上7歳6か月未満 1期追加:生後6か月以上7歳6か月未満 2期:9歳以上13歳未満 |
|---|---|
| 標準的接種期間 | 1期初回:3歳以上4歳未満 1期追加:4歳以上5歳未満 2期:9歳以上10歳未満 |
| 回数 | 1期初回:2回…6日以上あけて受ける 1期追加:1回…初回終了後6か月以上あけて受ける 2期:1回 |
※平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方は、接種時期に関する特例があります。詳しくは『日本脳炎予防接種の特例について』のページをご覧ください。
| 対象年齢 | 12歳になる年度初日から16歳になる年度末日までの女子(小学6年から高校1年相当)(注釈) |
|---|---|
| 標準的接種期間 | 13歳になる年度初日から末日まで(中学1年生) |
| 回数 | ■サーバリックス(2価)の場合 |
※平成9年4月2日から平成21年4月1日に生まれた方は接種時期に関する特例があります。詳しくは『ヒトパピローマウイルスワクチン接種の特例(キャッチアップ接種)について』のページをご覧ください。
持ち物
- 予診票(庄内町の予診票をお持ちでない方は、保健福祉課まで連絡ください。)
- 母子健康手帳
- マイナ保険証・資格確認書等
予防接種の受け方
事前に![]() 予防接種医療機関(PDF:256KB)にご予約ください。
予防接種医療機関(PDF:256KB)にご予約ください。
予防接種協力医療機関に記載のない県内医療機関での接種を希望される方
町が発行する接種券が必要です。接種する医療機関を事前に決めて、保健福祉課へ連絡ください。
県外の医療機関での接種を希望される方
事前に申請が必要です。詳しくは「県外予防接種」をご覧ください。
予防接種を受けることができないお子さん
- 明らかに発熱(通常37.5度以上)をしているお子さん
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、ひどいアレルギー反応(アナフィラキシー)を起こしたことがあることが明らかなお子さん
- BCG接種の場合においては、予防接種、外傷などによるケロイドが認められるお子さん
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
予防接種を受ける間隔について
注射生ワクチン接種後に異なる注射生ワクチン接種をする場合、27日以上の間隔が必要です。
(BCG、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、水痘など)
予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づく定期予防接種を受けた方に、万一、健康被害が発生した場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。
詳しくは、![]() 厚生労働省のWebサイト(外部サイト)をご覧ください。
厚生労働省のWebサイト(外部サイト)をご覧ください。
任意予防接種における健康被害の救済措置について
任意予防接種は予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法および町が加入する予防接種賠償補償保険に基づく救済給付の対象となります。
詳しくは、![]() 独立行政法人医薬品医療機器総合機構のWebサイト(外部サイト)をご覧ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構のWebサイト(外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
保健福祉課 健康推進係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0147

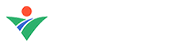
 くらしの情報
くらしの情報 行政情報
行政情報 産業・ビジネス
産業・ビジネス 観光・イベント
観光・イベント